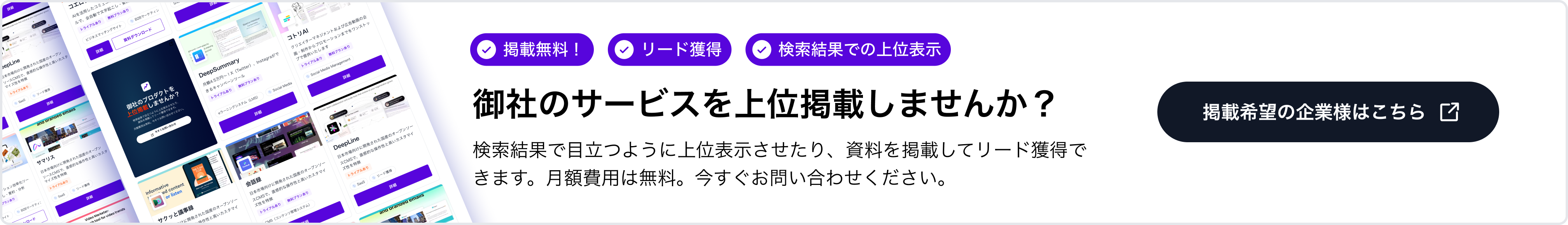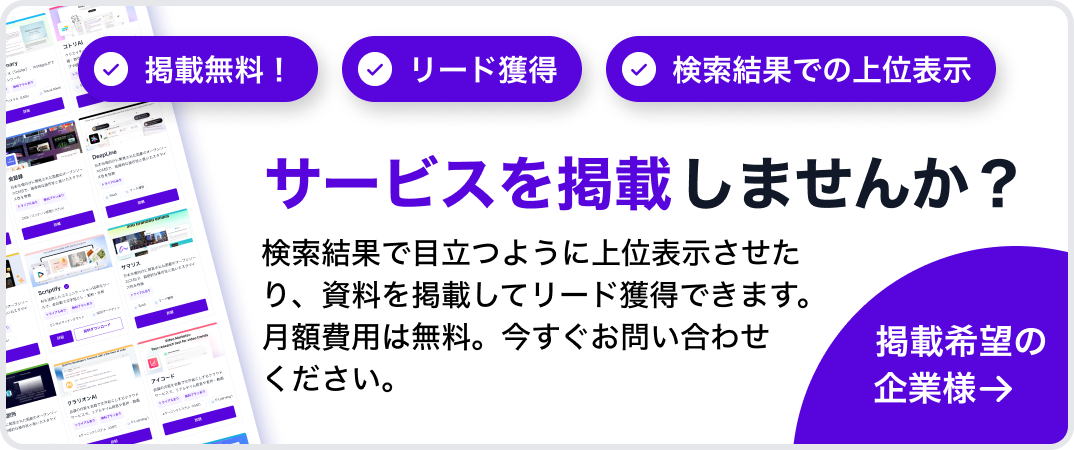厳選!AI研修の導入事例10選!研修後の効果や現場の声は?
更新日:
デジタルトランスフォーメーション(DX)が叫ばれる現代。企業の競争力は、AIをいかに活用できるかに大きく左右されます。 しかしアデコグループの調べでは、約7割の管理職が、日本のAI導入は諸外国に比べて遅れていると回答したことがわかりました。(※1) そんな中、「何から手をつければいいかわからない」「AIを扱える人材がいない」といった課題を抱える企業は、少なくありません。実際、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2024年に発表した『DX動向2024(※2)』によれば、約85.7%の企業が、DX人材の不足を感じています。AIに対応できる人材の育成は、急務です。 そこで本記事では、AI研修の基本から、具体的な導入事例、そして失敗しないサービスの選び方までを網羅的に解説。貴社のAI人材育成、そして事業成長の次の一手を見つけるための、具体的なヒントを提供します。
法人向けAI研修の主な4つの種類
AI研修は、対象となる従業員の役割に応じて、大きく4つのカテゴリーに分けられます。
| 研修の種類 | 主な対象者 | 目的・概要 | 学習内容例 |
|---|---|---|---|
| 全社員向け | ・全従業員(役職・職種問わず) | AIの基本知識や倫理の学習 | ・AIの歴史と基本用語 ・生成AIの業務活用入門 ・AI利用におけるコンプライアンス |
| 企画・マーケティング向け | ・事業企画 ・マーケティング担当者 ・DX推進担当者 | 自社の課題をAIで解決する力の養成 | ・AI導入企画の立案 ・ビジネス課題の分析手法 ・プロジェクトマネジメント |
| エンジニア・開発者向け | ・エンジニア ・プログラマー ・データサイエンティスト | AIモデルやシステムの開発スキルを習得 | ・Pythonプログラミング ・機械学習ライブラリの活用 ・クラウドでのAI開発 |
| 経営・管理職向け | ・経営者 ・管理職 | AIを活用した経営判断の迅速化・企業の成長力の強化 | ・最新AI技術の経営トレンド ・DX成功・失敗事例研究 ・AIを組み込んだ経営戦略の策定 |
1.全社員向け:AIリテラシー研修
全社員向けのAI研修では、すべてのビジネスパーソンのための基礎教養として、AIの基本的な仕組みや可能性、そして情報漏洩や著作権といった倫理的なリスクを学びます。全社的なAI活用の土台を築くのが、主な目的です。
2.企画・マーケティング向け:AIビジネス活用・推進研修
企画・マーケティング向け研修は、自社のビジネス課題をAIでどう解決できるかを考え、企画や販売促進活動を推進するための、実践的な内容が主体です。AIプロジェクトの勘所や費用対効果の考え方を学び、事業を動かす力を養います。
3.エンジニア・開発者向け:AIモデル開発・実装研修
Pythonなどのプログラミング言語を用いて、AIモデルやシステムを自ら構築するための高度な技術研修が、エンジニア・開発者向けです。企業の技術的内製化を目指し、競争力の源泉となる専門人材を育成します。
4.経営・管理職向け:AI戦略策定研修
経営・管理職向けの研修では、技術論ではなく、AIを活用して経営にまつわる戦略的な意思決定を下せるスキルの習得を目指します。ビジネス変革の観点からAIを学び、全社的な投資判断の精度を高めるためにAIをどう活用するのかを学ぶのが、主な目的です。
AI研修の主な3つの形式と特徴
AI研修には、さまざまな提供形式があります。ここでは、代表的な3つの形式をご紹介します。
| 形式 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 集合研修(オフライン) | ・指定会場で受講 ・対面式 | ・実践的なワークショップに最適 ・集中して学習に取り組める | ・時間や場所の制約がある ・コストが高くなる傾向 ・スケジュール調整が難しい |
| オンライン研修(ライブ) | ・Web会議形式 ・リアルタイムに受講。 | ・場所を選ばず全国から参加可能 ・チャットで気軽に質問できる ・録画による反復学習が可能 | ・受講者の通信環境に依存 ・長時間の講義では集中力の維持が課題 ・参加者同士の議論が深まりにくい |
| eラーニング | ・録画済みの講義動画で受講 ・個人のペースで視聴 | ・時間や場所の制約が少ない ・自分のペースで繰り返し学習できる ・全社など大規模展開時にコストを抑えやすい | ・受講者のモチベーション維持に課題 ・タイムリーな疑問点の解消が困難 |
対話の質や一体感を重視するなら集合研修、手軽さやコストを重視するならeラーニングと、求める要素によって選択肢は異なります。研修の目的や対象人数、予算などを総合的に考慮したう上で、最適なAI研修を選ぶことが重要です。
法人向けAI研修サービスの導入事例10選
1. オムロンソーシアルソリューションズ株式会社|国内グループ社員(管理職・一般・エンジニアなど)対象

全社的な生産性向上を目指すオムロンでは、国内グループ社員約1万人を対象に、スキルアップAIの「AIジェネラリスト基礎講座」と「AIプロジェクト・プランニング推進基礎講座」を導入しました。この研修は、一般・管理職・エンジニアといった受講者の役職や役割に応じて、カスタマイズされたAI研修を実施するものです。
その結果、受講後アンケートで満足度90%以上という高い評価を獲得。資料作成や情報収集の時間が短縮され、社員がより付加価値の高い業務に時間を創出できるようになった効果がありました。
研修の受講者からは「AIを自分ごととして捉える良いきっかけになった」「プロンプト作成のポイントが分かり、すぐに実践できた」といった声が上がっています。
出所:https://www.skillupai.com/private-training/success_stories/omron/
2. コニカミノルタ株式会社|管理職対象

コニカミノルタは、AI事業開発の加速を目的としてシナモンAIの5日間集中「AI戦略ワークショップ」を導入しました。8事業部から各事業部の管理職クラスを中心に、約50名が参加しています。
この研修では、AIプロジェクトのフレームワーク学習や、IDEOと共同開発した「デザインシンキング×AIハーベストループ」のビジネスモデル習得、グループでの事業戦略立案とプレゼンまでを実践しました。
その結果、8つの事業部で具体的なAI活用プランが策定され、事業化に向けた継続支援へと発展。これにより、失敗を最小化する開発モデルを理解し、AIを起点にDXを推進できる人材の育成が加速されるという効果がありました。
参加者した社員からは「失敗を最小化しながら進むリーン顧客開発モデルは、実業務でも使えると感じた」「ハーベストループ等の勝ち続ける仕組みを自社テーマの戦略へ反映させていきたい」といった声が上がっています。
出所:https://cinnamon.ai/news/20210204_aiseminar/
3. 株式会社城山|Webマーケティング担当の全メンバー対象

株式会社城山では、Webマーケティング担当者のスキルに差があり、チーム連携が困難な課題に対し、D-Marketing Academyの「デジタルマーケティング研修」を導入。Webの共通認識を醸成するため、営業出身者からEC経験者まで多様なメンバーがeラーニングで学習を実施しています。
研修を通じて、Webマーケティングの全体像と具体的な手法について、チーム内での共通認識が生まれました。さらに、自社サイトの課題分析や今後の施策について、メンバーが同じ目線で議論できるようになったのも、目覚ましい効果です。
研修を受けた社員からは、他社サービスと比べて「実例を交えた具体的なノウハウや実践的な内容が魅力だった」と好評でした。
出所:https://www.d-m-a.jp/case/2439735
4. 株式会社ニチレイ|国内の正社員対象

全社員のDXリテラシー向上を目標に掲げるニチレイでは、アイデミーのeラーニング「Aidemy Business」を導入しました。国内正社員3,500名を対象者に、必修の「DXブロンズ」から始まる階層別研修を実施する、という内容です。
社長自らが率先して受講したこともあり、当初計画より前倒しで、全社員が修了見込みになりました。次の階級への希望者も、予想の倍近く集まる結果となっています。これにより、社員の学習意欲が大幅に向上し、主体的なDX推進の文化が醸成される効果がありました。
基礎研修は特に好評で、次のレベルである「DXシルバー」への希望者が想定の500名を大幅に超える約900名に達するなど、社員の高い学習意欲が示されています。
出所:https://business.aidemy.net/ai-can/aidemy_business_nichirei/
5. 株式会社シムックス|会社代表・役員・経営幹部から事務員まで

株式会社シムックスは、全社的なITリテラシー不足という課題に対し、経営層から現場まで一貫した意識改革を目指しました。導入したAI研修は、役職別に4回に分けて実施。その中には部長や支社長といった、経営幹部が含まれています 。
例えば経営層は、インターネット・アカデミーが提供するカスタマイズ研修を通じて、DXの必要性や背景、他社事例などを学習 。これにより、全社にIT化を推進するトップダウンの意識付けがなされました。
研修後、受講者からは「既存業務をデータ化し、新規計画を自動化したい」といった、より具体的で前向きな声が上がるようになりました 。
出所:https://www.internetacademy.co.jp/case/case106.html
6. 丸紅株式会社|AIの企画立案担当が対象

全社的なAI活用の取り組みが広がる中、丸紅では、AVILEN社の階層別AI研修を導入しました。具体的には、AI導入の企画に必要な論点を中心にした、ハンズオン形式の「AIビジネス研修」と、プロジェクトをリードできるエンジニア育成を目指して、技術者向けにオンラインで「データサイエンティスト研修」を実施する、という内容です。
受講者の段階に合わせた研修により、多くの社員がAIに興味を持ち、新たな活用への取り組みが多数生まれる効果がありました。
研修の企画担当者は「研修の成果は、間違いなく会社全体のAIリテラシー底上げにつながっている」と、高く評価しています。
出所:https://avilen.co.jp/case-article/ai-business_marubeni/
7. 静岡ガス株式会社|全マネジメント層対象

静岡ガスでは、DX推進人材と経営幹部の連携を強化するため、株式会社キカガクの「マネジメント層向けDX研修」を導入。全マネジメント層180名を対象に、個別のツール操作ではなく、管理職として必要な知識と思考法を学ぶワークショップ中心の研修を実施しました。
その結果、DX推進部門とマネジメント層との間に「共通言語」が生まれ、これまで専門的で壁を感じていた議論が円滑になりました。また、経営幹部がDXを自分ごととして捉えるようになったことで、全社的な変革が加速する土壌が醸成される効果も報告されています。
研修担当者は「座学だけでなくワークを多く取り入れたことで、管理職が得た知識を使うところまで体験できた」と高く評価しました。さらに参加者のアンケートでは「他の方の具体的なプロンプトと結果を学べたのが良かった」「発表会方式は非常に良かった」といった声が多数、寄せられています。
出所:https://www.kikagaku.co.jp/blog/interview-shizgas-management
8. TOTO株式会社|DX推進組織メンバー対象

TOTOのトイレ空間生産本部は、DX推進組織内のスキル差拡大という課題に対し、株式会社STANDARDのDX個別教育プラットフォーム「TalentQuest」を導入。アセスメントで個々の弱点を特定し、必要な講座だけを短時間で学べるeラーニングを実施しました。
研修を終えて社内では、部署全体のDXマインドの醸成が加速。以前はあったDX施策への抵抗感が減少しています。またリテラシーが底上げされたことで具体的な議論が増え、新しい施策を進める際に多くの社員が協力的になる、というのも、研修の成果です。
受講者からは「自分の弱点をピンポイントで気軽に学べるのが良い」「トレンドも自然と入ってくるようになった」といった声が上がっています。
出所:https://standard-dx.com/post_case/toto
9. 三井化学株式会社|全社員対象

三井化学は、DXによる企業変革のため、アビームコンサルティングの「AI人材育成サービス」を導入しました。具体的には、全社員1万人向けの基礎eラーニングから、専門家を目指すデータサイエンティスト育成まで、階層別の研修を実施しています。
その結果、2025年度までに165人のデータサイエンティストを育成するという計画が順調に進捗。全社員のデジタルリテラシーが向上し、事業部門でのデータ活用や分析への理解が深まる効果がありました。
受講者からは「知識のレベルアップに役立った」という声が多数寄せられたほか、管理職からも「自社業務を想定した演習があり、非常に身近で学びやすい」と高い評価を得ています。
出所:https://www.abeam.com/eu/ja/case_study/cs140/
10. 裕幸計装株式会社|希望者が対象

裕幸計装には、社内でAIへの関心が高まる一方、具体的な活用法が分からない課題がありました。これを克服するために、東京都のデジタル化支援事業を通じてトランスコスモス株式会社が運営する「中小企業向けAI入門講座」を導入。様々な部署から10名以上の希望者が参加し、動画学習と対面ワークショップを組み合わせた研修です。
研修後は、AIに任せるべき仕事とそうでない仕事が明確になり、受講者がAI活用の具体的なイメージを掴めるように。さらに、これまで検索エンジンを使っていた情報収集をChatGPTに切り替えるなど、社員がAIを使うことへの心理的障壁がなくなり、業務効率化につながる効果がありました。
受講者からは「講師が親身に実践的なアドバイスをくれた」と好評です。なお研修中は「時間がオーバーするほど活発な議論が行われ、非常に充実した時間になった」と報告されています。
出所:https://tokyo-digital-reskilling.jp/voice/voice_yuko.html
AI研修サービス選定で失敗しない3つのポイント
数多あるAI研修の中から自社に最適なものを選ぶために、外せない3つのポイントをご紹介します。
1.【目的の明確化】「研修で何を達成したいのか」を具体的にする
まずは、AI研修を導入する目的の解像度を上げましょう。「AIリテラシー向上」のような、漠然とした目的では、研修がただ受けただけで終わる懸念があります。
例えば、「営業部門の提案書作成時間を一人あたり月5時間削減する」「問い合わせの一次回答をチャットボットで80%自動化する」といったように、測定可能で具体的なビジネスゴールにまで落とし込むことが重要です。この明確なゴールが、最適な研修内容や対象者を選ぶ上での、揺るぎない指針となります。
2.【研修内容を吟味】カリキュラムは「実践的」か、講師は「プロ」か
目的が定まったら、それを達成できるカリキュラムかを見極めます。重要なのは、自社の業務に合わせた内容にカスタマイズできるか、座学だけでなく手を動かす実践的な演習が豊富か、という点です。
さらに、講師の質もチェックしましょう。AI技術に詳しいだけでなく、ビジネス現場での成功も失敗も知る経験豊富なプロを選ぶと、高い学習効果につながります。
3.【信頼性の確認】導入実績と「研修後」のサポート体制
サービスの信頼性を測る上で、導入実績は重要な指標です。特に、自社と同業界・同規模の企業への導入実績があれば、貴社の課題や文化への理解度が高いと期待できます。
また研修は「受けて終わり」ではありません。知識を現場で定着させるには、研修後のサポート体制が不可欠です。研修効果を最大化させ、持続的な成果につなげるなら、質問可能な相談会や継続的に学べる機会の提供など、伴走サポートが充実したAI研修を選ぶことが推奨されます。
まとめ
法人向けAI研修は、企業のAI人材を育成するための戦略的投資です。その成功の鍵は、全社員のリテラシー向上から経営層の戦略策定まで、研修内容を企業の目的別に設計することにあります。サービス選定では「目的の明確化」「実践的な内容」「研修後のサポート」の3点が不可欠です。
多くの先進企業がAI研修を起点に、生産性向上や事業変革といった具体的な事業成果につなげています。未来の競争優位性を築くために、まずはAI人材への投資から始めてみてはいかがでしょうか。
※1 出典:https://www.adeccogroup.jp/pressroom/2021/0204
※2 出典:https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/discussion-paper/dx-talent-shortage.html
公式SNSをフォロー
最新のAIトレンドやリリース情報をいち早くお届けします。
今すぐフォローしましょう!
関連タグ
この記事の著者
O!Product編集部
「O!Product(オープロダクト)」は、日本最大級BtoBのAIツール・サービス検索サイトです。 「日本のすべての企業に、AIトランスフォーメーションを。」をミッションに掲げているGigantic Technologies株式会社によって運営されています。 AIに精通し、2017年設立時から企業のDX支援に取り込んでおり、十分な実績とノウハウを元に情報を発信しています。
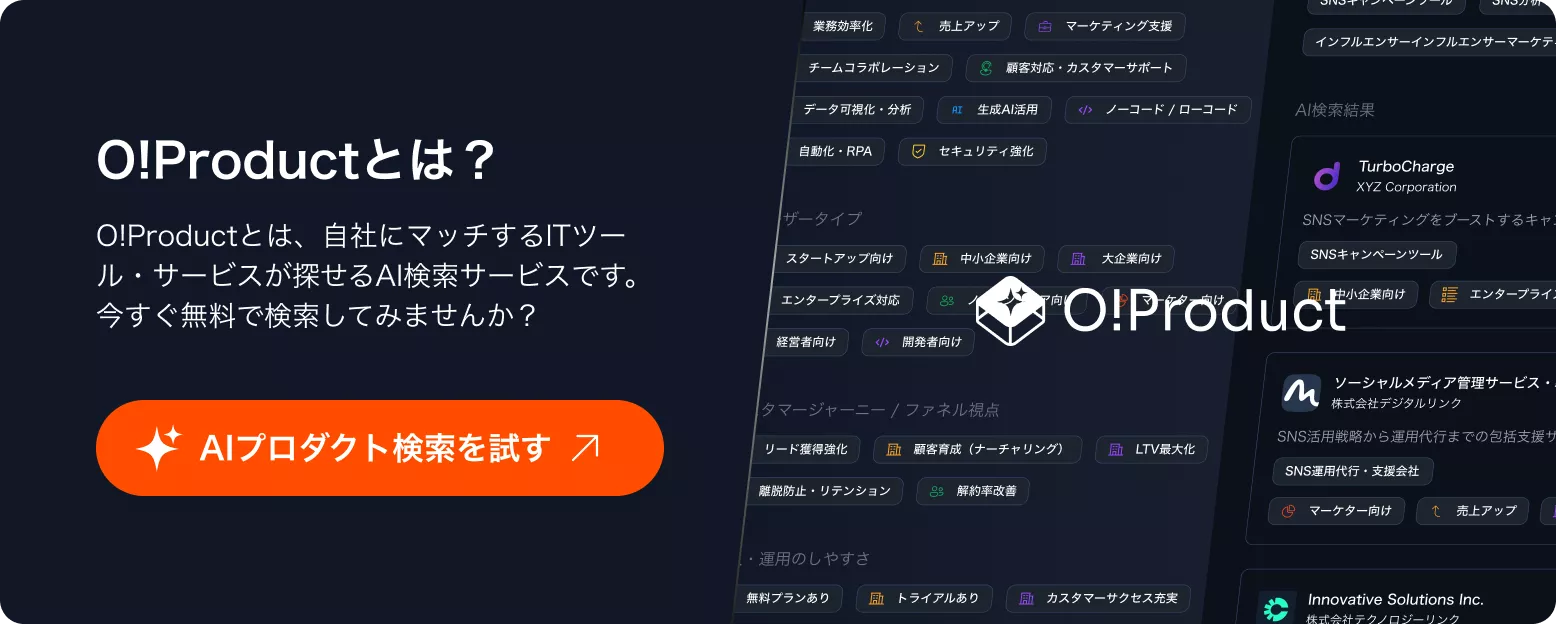

あわせて読みたい特集・コラム
【BtoB】人気の生成AI研修おすすめ10選!【2025年】
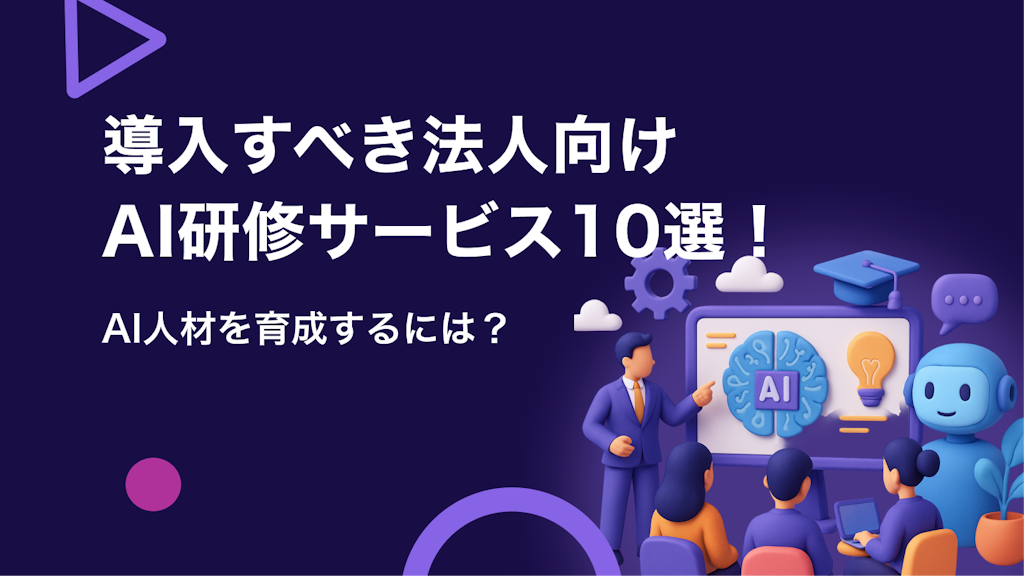
生成AI導入支援会社おすすめ14選【2026年最新版】事例・選び方も解説

Dify導入支援会社おすすめ12選 | 事例・選び方も解説【2026年最新版】